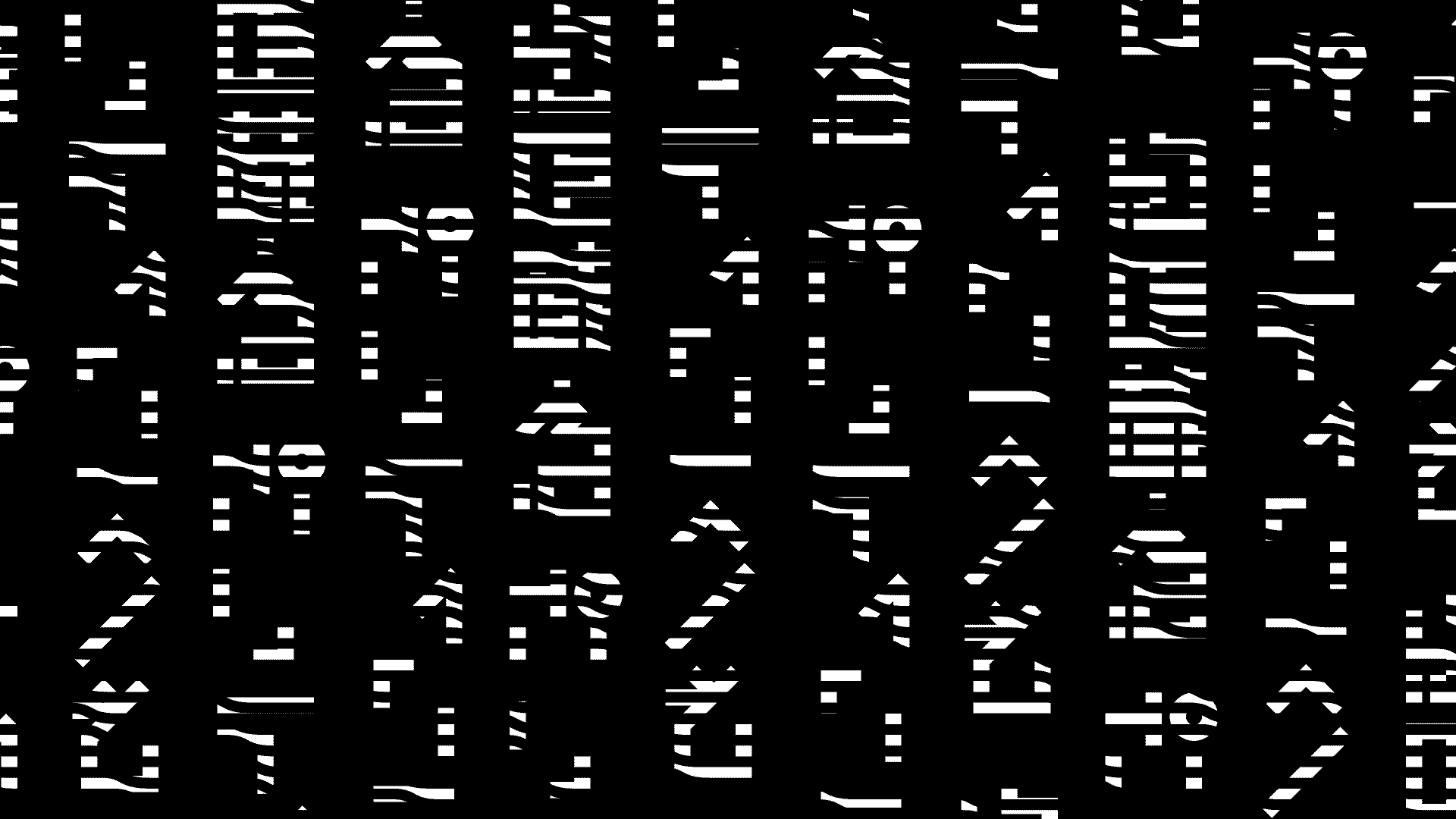『忠臣蔵・急 ポリティクス/首』は2014年の『櫻姫』を第1弾として始まった「現代日本演劇のルーツ」の第9弾である。本シリーズは第1弾以降『四谷怪談』や『盟三五大切』などの鶴屋作品を経て、近松作品や『忠臣蔵』に取り組み、6年間続けられてきた。シリーズ開始の発端に筆者が鶴屋南北の『桜姫東文章』の現代化を提案したことがあるという縁で、古典を現代化する劇団の姿を再考させていただくこととなった。
そもそも提案をした理由は、エイチエムピー・シアターカンパニーが当時「同時代の海外戯曲」シリーズとして、『最後の炎』(ドイツ)や『アテンプツ・オン・ハー・ライフ』(イギリス)などの海外のポストドラマ的な作品を上演していたことにある。一筋縄では読み解けない作品と向き合い、「今現在」と接続しようとする劇団の姿勢に、この劇団が古典と向き合うとどう表現するのだろうか、という好奇心があった。以降、「現代日本演劇のルーツ」を縦糸に、「同時代の海外戯曲」を横糸に、劇団は上演を重ねてきた。
稽古の開始は研究会を開催して原作を理解するところから始まる。これはこの劇団の普段の方法論で、しっかりと作品世界を知った後に、徐々に現在へと接続させていくのである。戯曲の翻案は主に劇作家のくるみざわに依頼した。くるみざわは、狂言に描き込まれた差別や暴力、階級社会やハラスメントの構造に焦点を当てて現代と結んだ。それゆえ「現代日本演劇のルーツ」シリーズは、現代社会を鋭く批評する作品群となってきた。
くるみざわの劇世界はリアリズム演出と親和性のあるような筋道の明白さがあるが、演出の笠井がそれを戯画的に表現する点が興味深い。もともとルコック・システムを取り入れた身体表象を用いてはいたが、近年は映像の文字を人物のように扱ったり、リミテッド・アニメーションを身体化したようなコマ送りに似た動きで演じたり、特注の太いゴムで作られた装置を用いたりと、その手法に幅が増してきた。くるみざわの紡ぐ日本語にからだを添わせるのではなく、美的な様式を持ち込むことでからだと日本語の距離を操る。そうすることで、観ている方は舞台が主張する現代社会への批評にのめり込むことなく、冷静に受け取ることができるように思われる。
最も大変なのは俳優たちかもしれない。研究会で古典世界を咀嚼し、くるみざわの政治性の噴出を抱きとめて消化し、笠井の美的な表現技法で言葉を裏ごしし、さらに独自性を上乗せしつつアンサンブルとして世界を立ち上げるための微調整を重ねる。時空を超えた四次元の綯交ぜがそのからだの中に生じているに違いない。時折なじみの劇団員と話をする機会を得ると、現代劇と同列の近しさで古典や政治を語る姿に6年の継続の力を感じさせられる。
ある国に暮らすからといって、その国の古典を自分と関連付けて身体化する必要が必ずしもあるとは思わない。自分のルーツは自分で選択をすれば良い。ただ、自分が暮らす国の社会構造の在り方を考える時に、古典を参照することは有効であろう。このシリーズは現代日本演劇のルーツが歌舞伎であると主張しているのではなく、現代日本のルーツを演劇で考えようと提案しているように感じられる。今回結末を迎える『忠臣蔵』三部作は、天皇制へとつながる制度の問題に深く切り込み、まさしく現代日本の来し方を考えさせられるものとなっている。どう決着をつけるのか、楽しみである。
岡田蕗子(大阪大学招へい研究員[演劇学])