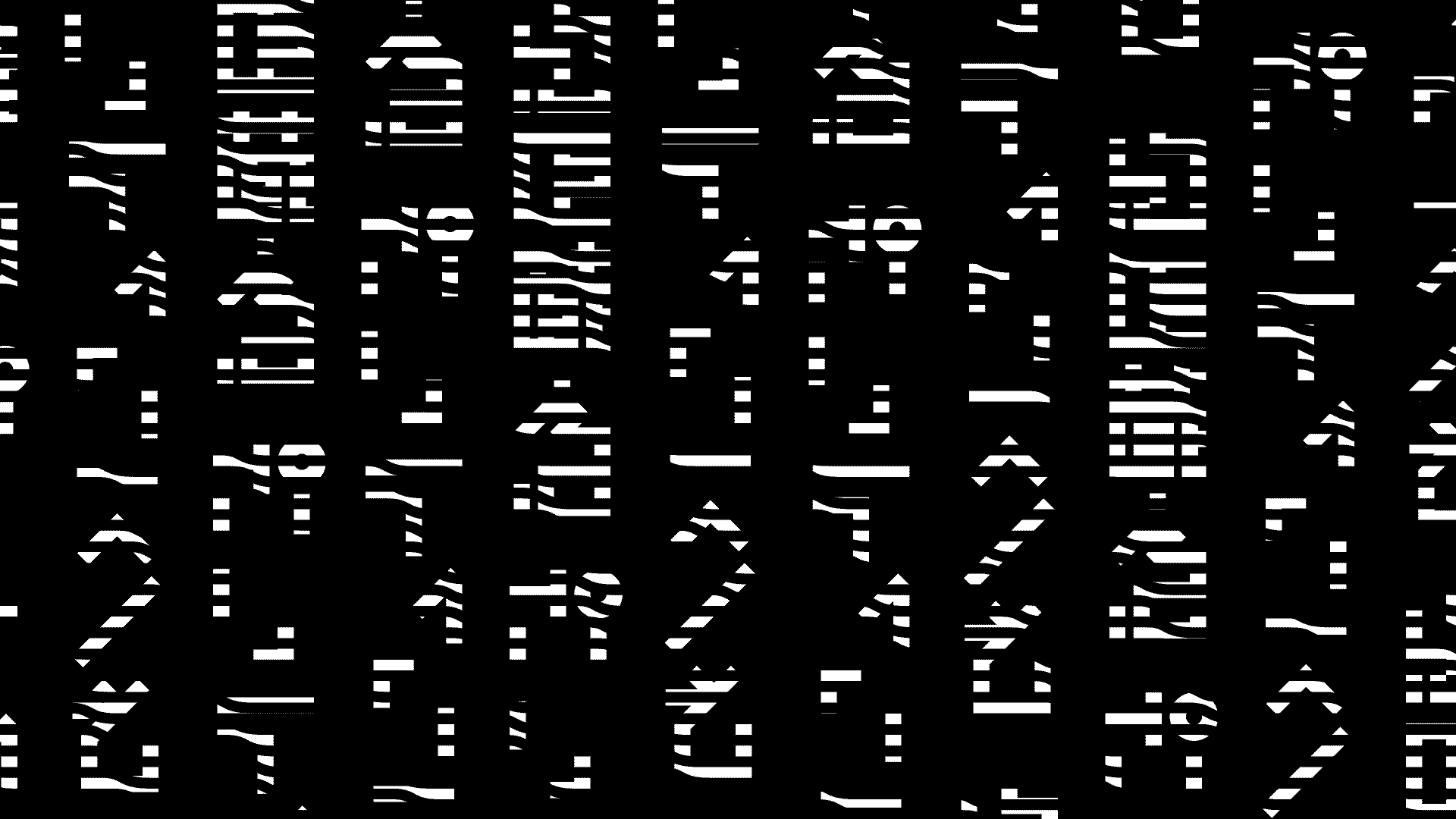ある程度の年配の人なら、「忠臣蔵」と聞いて、大石内蔵助以下四十七士が元禄15年(1702)12月14日に主君の仇、吉良上野介邸を襲った事件を思い浮かべるだろう。また、「赤穂事件」すなわち元禄14年の浅野内匠頭による吉良上野介刃傷と翌年の討ち入りは、高校の日本史の教科書に載っていて、現代の高校生も知っている。だが、「赤穂事件」の代名詞として用いられる「忠臣蔵」の語が人形浄瑠璃(現在の文楽)の作品『仮名手本忠臣蔵』に由来すること、しかし、その『仮名手本忠臣蔵』には、吉良上野介も浅野内匠頭も大石内蔵助という名前の人物は登場しないこと、そして、それは何故なのか、を知る人は、文楽や歌舞伎の愛好者か演劇を学んだ人に限られるかもしれない。一方で「忠臣蔵」という言葉を聞いたことがないという人は少ないと思う。このあたりが現代における「忠臣蔵」の認知度になるのだろうか。
人形浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』は寛延元年(1748)8月、大坂竹本座で初演された。「赤穂事件」(刃傷)から47年目であった。「赤穂事件」の劇化は事件の直後から行われ、事件から今日までの270年余りの間に創られた「赤穂事件」の作品は、演劇、話芸、歌謡、小説、映画、ドラマ、バレエ、オペラ、漫画、ゲームに及び、おびただしい数に上る。『仮名手本忠臣蔵』は、その中にあって、人形浄瑠璃黄金期の最高傑作として屹立し、「赤穂事件」作品の分水嶺となった作品である。「赤穂事件」作品が現在でも「忠臣蔵もの」と呼ばれるのはこのためで、ウィキペディアでも「忠臣蔵」の項に「赤穂事件を題材とした作品」の章がある。
徳川幕府を揺るがせた「赤穂事件」の作品化はもちろん禁じられていた。元禄16年(1703)2月に出た「以前にも命じたように、『当世異事』を歌にしたり、それを出版したり、また上演してはならない」という禁令の記録がある。つまり、禁令が何度も出されるほど作品が出たということである。元禄16年(1703)、50歳だった近松門左衛門は、京都で歌舞伎「傾城三の車」に討ち入りを示唆する場面を描き、そして、宝永7年(1709)には大坂竹本座に人形浄瑠璃作品「兼好法師物見車」とその後段「碁盤太平記」を書いて、「赤穂事件」を作品化した。この作品では「赤穂事件」が、「当世(=現代)」の事件としてではなく、南北朝の騒乱を描いた「太平記」を下敷きに室町時代のこととして描かれており、高師直(吉良上野介を仮託)が塩冶判官(浅野内匠頭を仮託)の妻を横恋慕することが発端となって事件が起こり、大星由良之介(大石内蔵助に当たる)が討ち入る。事件から半世紀の間に「赤穂事件」を題材として、仮託の設定も登場人物名も異なるいくつもの浄瑠璃と歌舞伎の作品や小説類が作られ、人気の場面も生まれた。『仮名手本忠臣蔵』はそれらが集大成された作品で、「太平記」を下敷きにした設定を踏襲し、師直の塩冶の妻顔世への横恋慕を事件の発端としている。だから、吉良や浅野や大石という名前は出てこないのである。事件後半世紀を経て生まれた『仮名手本忠臣蔵』の魅力は、仇討ちを縦軸に事件をめぐる人々のドラマを情感豊かに描いているところにあり、ドラマの鍵を女性の登場人物が握る。
『仮名手本忠臣蔵』後にも「忠臣蔵もの」は続々と作られた。今日でいうスピンオフものが多い。鶴屋南北も「忠臣蔵もの」を小説も含めて数作作っており、やはり「現代日本演劇のルーツ」シリーズで上演された「東海道四谷怪談」や「盟三五大切」は南北の「忠臣蔵もの」の歌舞伎作品である。近代に入ると、登場人物は実名で書かれるようになり、さらに様々の角度から「赤穂事件」が描かれるようになる。
エイチエムピー・シアターカンパニーの「忠臣蔵 序・破・急」三部作はその流れに連なる最も“新しい”「忠臣蔵もの」の作品になる。新しい作品は常に過去の作品に新たな光を当てる。エイチエムピー・シアターカンパニーの「忠臣蔵」三部作もまたしかり。ついに女優だけで上演される男しか登場しない「忠臣蔵」の《急》や如何に。
林公子[近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻教授]