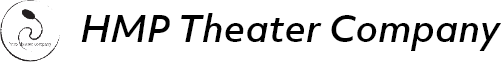シンメルプフェニヒにおける「語り」とは? 文・大塚直(愛知県立芸術大学音楽学部教授)

『アラビアの夜』の作者 ローラント・シンメルプフェニヒにおける「語り」について、翻訳者の大塚直さんにコラムを執筆いただきました!
西洋戯曲史の流れを踏まえつつ、シンメルプフェニヒの「語り」について紹介してくださっています。
観劇前後にぜひご覧ください。
___________________________________________
そもそも演劇において、なぜ「語り」が問題になるのでしょうか?
西洋において文学は歴史的に「抒情詩」「叙事文学(小説)」「劇文学」という三つの大きなジャンルに分けられてきました。そのうち演劇を構築する劇文学、すなわち戯曲とは、人と人との間で行われる「対話」を扱う文学ジャンルとして規定されてきたのです。
そのため「語り」、物語る、とはむしろ叙事文学の範疇であり、その一方で戯曲という閉じた古典的な演劇形式は、対決する劇的な構造を持ち、純粋にそれ自体を表出するものと考えられてきました。すなわちドラマとは、観客とは関わりなく自立的に、しかし同席した観客を巻き込んで感情移入させながら、絶対的な現在のなかで進行する文学ジャンルだったのです。例えばアリストテレスも『詩学』のなかで「悲劇を叙事的に描き出さないように」と注意を促しています。
しかし時代が下って19世紀に盛んになるのは、新聞などジャーナリズムの発達を前提にした、小説というジャンルでした。従来の理想主義的な「市民悲劇」はおのずと低調になり、次第に《ドラマの危機》と呼ばれる時代様相を呈していきます。なぜならば、世界秩序や普遍的な価値体系を前提にして、強烈な意思を備えた英雄像を描いてきた「悲劇」は、大衆社会の到来と同時に自由と引き換えにして、次第にこの秩序自体を失っていったからです。
そして従来の身分制社会や経済格差などに批判的な目が注がれるようになると、偉大な人物に寄せる同情やカタルシスといった悲劇の理論も、社会の底辺から眺めると偽善的で色褪せたものとして目に映るようになりました。この時代に新しく生まれたビューヒナーらの「社会劇」は、断片的で開かれた構造を持ち、ドラマは叙事的な傾向を示すと同時に、従来の劇的な形式を失いましたが、逆に観客に対して社会分析的な視座を提供するようになりました。
ペーター・ションディに従えば、イプセンやチェーホフらの20世紀初頭に書かれた戯曲はすでに明確に「叙事化(Episierung)」の傾向を示していますが、それを新しい演劇理論として体系化したのがブレヒトでした。ブレヒトは第一次世界大戦という悲惨な経験から、祖国のための美しき自己犠牲や、悲劇の主人公への自己同一視から生まれる英雄的な死を毛嫌いしました。卑怯であっても生きのびて人生を享受せよ、というのがブレヒトの首尾一貫した立場だからです。
こうして生まれた彼の「叙事的演劇」では、悲劇に寄せる感情移入の危険性を踏まえて、観客には距離を取って批判的に舞台を観察させる手法が取り入れられました。俳優はもはや「役柄」になりきるのでなく、「役柄」に対しても批判的に距離を取る必要がありますし、観客もまた、「筋」の経過を辿るよりも、登場人物たちが置かれた「状況」を冷静に観察して、世界を変革すべく取り組まなければなりません。ドラマの絶対性よりも、演劇自身による自己省察が重視され、戯曲においても対話的構造よりも、ナラティヴ(語り)のほうが優勢になっていったのです。
また「叙事的演劇」においては、従来のリアリズム演劇のように、まるで「第四の壁」に遮断されたイリュージョン形式の舞台が創造されて、鑑賞によって感動が蓄えられるというのではなく、観客もまたモデル劇に参加して主体的に問いかけ、共に社会について考える道が拓かれました。盟友ベンヤミンはブレヒト劇について「観衆の誰でもが、共演者になれるだろう」と指摘しています。

さて戦後になると、1970年代からパイマンやツァデクらの「演出家演劇」が興隆を見せ、演出上の立場から文学テクストを自由に裁断化していくなど、古典戯曲の新解釈が行われるようになりました。
さらに1980年代になると、新しいメディア環境の普及を背景にして、後にハンス=ティース・レーマンによって「ポストドラマ演劇」と呼ばれる多彩な上演スタイルが顕著になっていきます。これは単なる戯曲の新解釈ではもはや不十分であるとし、従来は演劇を構築するうえで上位審級にあった戯曲、文学テクストを、演出上の立場から脱文学化、演劇のための素材として自由に扱うことを意味し、伝統的に戯曲を中心に据えて上演が行われてきた西洋演劇の慣習からのパラダイムシフトとなっています。
舞台上での虚構と現実の区別という約束事も、次第に放棄されるようになり、演劇では俳優や観客と共に、パフォーマンス性と直結した一回性の何かが成立するだろう、といった理解のもとで、テクスト以外のビデオ映像やダンスなど、様々なメディア表現を戯曲と併存・競合させる新しい《上演の美学》が重視されるようになりました。俳優と役柄との関係性を問いに付すハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』などは、このような西洋戯曲史の流れのなかで生み出されているのです。
ところが2000年前後から、デア・ローアーやマイエンブルクら当時の新しい世代によって、ふたたび革新的な戯曲、演劇テクストが書かれるようになり、演劇における《テクスト性の回帰》として注目を浴びました。とくにローラント・シンメルプフェニヒの戯曲では、一見すると時・場所・筋の一致など古典的なドラマのスタイルに回帰しているようでありながら、「ポストドラマ演劇」の一連の成果、映像の技法や音楽の使用など現代的な舞台実践の特徴をあらかじめ演劇テクストに落とし込んだかのような、斬新な作劇法が見て取れます。そこでももちろん、単なるテクストの再現や、リアリズム演劇が志向されているわけではなく、イマジネーションをその場に居合わせた観客と共有する作劇法、一回性の生の舞台を生み出す「設計図」として戯曲のあり方が捉え返されています。
そんなシンメルプフェニヒの代表作、上演回数から言っても『金龍飯店』と並び称される傑作が『アラビアの夜』です。この芝居では夏の夜の高層マンションを舞台として、五名の人物が登場しますが、もはや伝統的な俳優同士による「対話」ではなく、基本的にはそれぞれが今、自分の置かれている状況を簡潔に「語りかける」、すなわち心の声として順次、説明ないしは報告するスタイルで舞台が進行し、その多方面に向けられた「語り」、孤独な声が次第に舞台上で交響し合って、予期せぬ形で繋がっていきます。

つまりシンメルプフェニヒにおいて、戯曲はナラティヴ(語り)を基調とすることでふたたび文学性の優位に立ちながら、しかしテクストの語り手はそのまま演じ手へと移行して、さらに「語り」は次第に日常の現実世界を侵食し、演劇実践の決まり事を飛び越えて、最終的には俳優の童心に帰ったかの演技と観客の自由な想像力とによって、舞台は一種シュールレアリスム的な幻想世界へと至るのです。
また、こうした遊び心、語りと行動による二重化、反復、戯曲の中での自己言及性といった手法で、シンメルプフェニヒは演劇におけるブレヒトの「叙事化」の傾向をさらに推し進め、「語り」という太古の演技形式を用いることで、現在ラジカルに戯曲を「物語化(Narrativierung)」していると言えるでしょう。
このような「語り」を今回、笠井さんがどのように舞台化したのか、楽しみなところです。