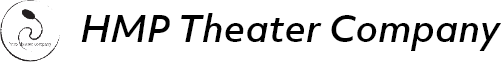今回の上演によせて 文・笠井友仁

今回の企画のはじまり
エイチエムピー・シアターカンパニーは2021から2023年まで<シェイクスピアシリーズ>に取り組んできましたが、ウイングフィールドさんから「ウイング再演大博覧會2024」の提案があり、過去作品の中から再演できる演目を選ぶことになりました。そこで2017年2月にDIVEプロデュースで上演した『メイド・イン・ジャパン』に取り組むことになりました。
『メイド・イン・ジャパン』は、エイチエムピー・シアターカンパニーが2013年から繰り返し上演しているドイツの劇作家ローラント・シンメルプフェニヒの『アラビアの夜』を参考にして、笠井から土橋淳志さん(A級MissingLink)に執筆を依頼した、「語り」に注目した作品です。『メイド・イン・ジャパン』を再演するなら、そのきっかけになった『アラビアの夜』も同時に上演し、「語り」の魅力について考えてみようということになりました。
そこで2作品を同時に上演するプロジェクト名を<都市をかたどる劇文学>としました。2作品とも登場人物による対話が極端に少なく、俳優が観客にむけて現在の状況や過去のできごとを語ることで物語が進行していきます。物語ることによって舞台と観客席のあいだに浮かび上がってくる数々のイメージ。そのイメージが重なり合うことで感じられる劇文学の世界をお楽しみ頂きたいと思っています。
「語り」のおもしろさ
「イメージが重なり合うことで感じられる劇文学の世界」と言いましたが、これを観て頂くみなさんにどう楽しんで頂くか、が今回のテーマです。ことばが中心になるため、ややこしい、むずかしそう、と考える人も少なくないと思いますが、そこになんとか挑戦して、「語り」のおもしろさを感じて頂きたいと思います。
このように考えるようになったきっかけは、数年前から始まった常磐津節とのコラボレーションです。確かにエイチエムピー・シアターカンパニーは以前から、「リアリズム演劇」にみられる「対話」よりも、『ハムレットマシーン』の独白など、「語り」の方に関心があったと思います。しかしそれに自覚的になっていったのは、常磐津節や人形浄瑠璃の作品に触れたことが大きいと思います。
「語り」という視点で舞台芸術を見渡せば、多様で自由な表現があることにあらためて気づきます。今回の同時上演を通じて「語り」のおもしろさ、フィクションの持つ可能性を探り、その成果を関係者はもちろん、観客のみなさんと共有したいと思います。
『メイド・イン・ジャパン』
『メイド・イン・ジャパン』の執筆を依頼する際、わたしは「モノローグ」を中心に劇作をして欲しいと土橋さんにお願いしたと思います。実際には様々な「語り」があるのですが、当時のわたしはそのように表現していたと思います。そこで土橋さんは、撮影者というひとりの登場人物がある事件の真相を探るため、インタビューを行い、その取材対象者が次から次へと物語るという作品を書いてくれました。
登場人物たちの語りから見えてくるのは、日本の虚像です。メイド喫茶のメイドから始まり、オタク文化や日本の神話など、日本にまつわるイメージが次々と語られます。そして、いずれもが人々によって作られたイメージであることがわかります。それは「本物とは何か」、「本物などあるのか」という問いかけだと思います。

出演者について
今回『アラビアの夜』は戯曲に書かれているとおり、5名の俳優が出演します。しかし同時に上演する『メイド・イン・ジャパン』は、素浄瑠璃を参考にして、10名の登場人物を2名で語ることにしました。そのために『メイド・イン・ジャパン』は、俳優が戯曲を手元に置いたまま、パーカッションの演奏とともに表現します。少しおかしなスタイルだと思われるかも知れませんが、日本にまつわる虚像を扱った戯曲を表現するのに適していると考えています。実際にどのような試みになったか、ぜひご覧頂きたいです。
『アラビアの夜』
『メイド・イン・ジャパン』は、10名の登場人物の証言から、ひとりの女性の姿が浮かび上がる物語です。また、女性の姿が見えてくると同時にそれが虚像であることも感じられる作品です。それに対して『アラビアの夜』は、5名の登場人物が住居はもちろん、階段やエレベーター、エントランスなど、11階建ての高層マンションの中を移動しながら、普段の暮らしの中に『千夜一夜物語/アラビアンナイト』のおはなしが溶け込んできて、リアルとフィクションが交錯する作品です。
「語り」とは何かⅠ~シンメルプフェニヒの「対話」
さて、ここからは、やや長くなりますが、2013年から取り組んでいる『アラビアの夜』から「語り」についてどのようなことを考えたのか、お話したいと思います。
作品を創作するうえで「語りとは何か」を自分たちなりに考える必要がありました。そこで、今回上演する『アラビアの夜』の作者、ローラント・シンメルプフェニヒの考えを理解することから始めました。
翻訳者の大塚直さんの解説文や論文を読むと、どうやらシンメルプフェニヒは「リアリズム演劇」に懐疑的です。しかし「対話が演劇の核」とも言っています。さらに演劇はスペクタクルを目指すのではなく、「演劇独自の魅力を発揮するべきだ」とも言っています。彼にとってその答えが「語りの劇」のようです。
ところで「対話が演劇の核」であるならば、舞台上で行われる対話を中心に劇をつくる「リアリズム演劇」を、どうして否定するのでしょうか? そもそも彼の言う「対話」とは一体何でしょうか?
この点を出演者と話し合い、翻訳をなさっている大塚直さんからも意見をもらいました。
すると、シンメルプフェニヒの言っている「対話/dialog」が、舞台上で行われる対話ではなく、「演劇と社会あるいは舞台と観客の対話」であることがわかりました。同時にシンメルプフェニヒは、戯曲をパフォーマンスのための「設計図」と考えており、戯曲に「リアリズム演劇」のような再現を求めていないことがわかりました。シンメルプフェニヒは戯曲をもとにライブ感のあるパフォーマンスを創作し、それを観客に楽しんでもらい、舞台と観客の対話を実現しようと考えていたのです。

「語り」とは何かⅡ~閉じられた対話と開かれた対話
そこで舞台上で行われる「登場人物同士の対話」と「舞台と観客の対話」を区別することにしました。
舞台上の限定した空間で行われる前者を「閉じられた対話」、そして「閉じられた対話」に対して、より広い空間で行う後者を「開かれた対話」と呼ぶことにしました。またシンメルプフェニヒの考えを活かすため、今回の上演は「開かれた対話」を積極的に用いることにしました。
少しだけ「閉じられた対話」と「開かれた対話」の例を挙げておきたいと思います。舞台上の限定した空間で行われるか否かがその境界です。よって多くの「リアリズム演劇」で「閉じられた対話」が用いられています。もちろん演目や演出によって異なりますし、場面によって「閉じられた対話」から「開かれた対話」へ、あるいは逆と、うつることもあります。「開かれた対話」にはテントで行われる小劇場演劇や漫才などがあります。落語は多くの場合、「開かれた対話」からはじまり、「閉じられた対話」と「開かれた対話」を行き来する芸だと思います。
このふたつは異なる性質を持っているため、どちらが優れているというものではありません。虚構の中に誘う「閉じられた対話」の方が観客の強い共感を得やすく、虚構と現実が重なり合う「開かれた対話」の方が、ものごとを再認識する、異化する力が働きやすいのではないか、とわたしは考えています。また「開かれた対話」は演じている俳優と観客が直接出会う機会だと考えています。つまり「開かれた対話」は俳優と観客が互いにその存在を認識することになります。
「語り」とは何かⅢ~設計図としての戯曲
翻訳者の大塚直さんによると、シンメルプフェニヒはあくまで劇作家であり、パフォーマンスに高い関心があるが、戯曲や小説を書くことで創作に関わりたいと思っている、とのことでした。つまり文学性をとても大事にしているのです。ただしパフォーマンスに文学の再現を求めているわけではありません。また、作品を観客のみなさんに楽しんでもらいながら、観劇後に観客が何かを持って帰るような作品を目指しているようです。
現在、現代演劇の置かれている状況は大変厳しいと思います。エンターテインメントはますます充実し、テレビ、映画や映像コンテンツ、街を活かした企画やプロジェクション・マッピング、そして巨大な会場を使ったスペクタクル性のある催しなど、多岐に渡ります。
もちろん現代演劇とこれらのエンターテインメントは楽しみ方が異なるので簡単に比較できませんが、その違いを理解して、舞台芸術の価値を再発見していくことが必要だと思います。伝統演劇やミュージカル、他の現代演劇と比べて、わたしたちの劇団にどのような特徴があるのか、常に考えていきたいところです。
ウイングフィールドさんの「ウイング再演大博覧會2024」に参加し、過去作品を見直す機会を頂いたわけですから、「語り」に注目したシンメルプフェニヒの「設計図」をかりて、自分たちなりの表現を探っていきたいと思います。そしてその成果を観客のみなさんに楽しんで頂きたいです。

フィクションを楽しもう
最後に「フィクションを楽しもう」というテーマについて話したいと思います。演劇はいつもフィクションなのですが、演劇を現実の模倣とみることもできるため、現実っぽさ、リアリティが求められることが多くあります。
産業が発展し、現実そっくりの空間がつくれるようになると、よりリアルな表現が求められるようになります。演劇でも「リアリズム」という表現方法が定着しており、リアルな演技が求められる創作現場も少なくありません。その場合、俳優は登場人物に「なる」ことを求められます。
ここでいう「なる」とは一致するということです。もちろんフィクションですから登場人物に完全に一致することはありません。できるだけ役に近づく、もしくは他の人から一致しているように見えることを目指して演じることになります。「役を生きる」と表現する人もいます。そこには俳優自身が何かになりたいという願望もあるのかも知れません。
このような俳優と役が密着した状態は「開かれた対話」にはむきません。役に「なる」のではなく、役の特徴を表現するようにして欲しいのです。そのため、ときには一致しているように見えることもありますが、俳優と役の距離はある程度離れた状態にあります。あるいは一致した途端に離れていくイメージです。フィクションであることを意識することが大事です。
このようにフィクションを意識して、虚構と現実が重なる利点を活かすことで、フィクションをより楽しむことが今回の上演の目的のひとつです。
戯曲の忠実な再現を目指すのではなく、『アラビアの夜』と『メイド・イン・ジャパン』を設計図として捉え、開かれた対話を活かしたパフォーマティブな作品を目指したいと思います。