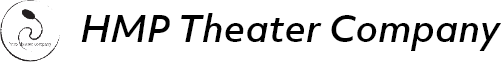『堀川、波のつづみ』作者のことば
とある劇作家が、こう言った。
「二種類の精神的な法、二種類の良心がある。一つは男のもの、もう一つはまったく異なる、女のもの。両者は互いを理解しない、しかし女は実際生活において男の法で裁かれる、あたかも男であるかのように。(略)女は現代社会において自己を全うすることができない。これは徹頭徹尾、男性社会だからである。法律は男が作り、検事も裁判官も男であって、女の行動を男の立場から裁く。」(「現代悲劇のための覚書」より)
その劇作家とは、ヘンリック・イプセン。『人形の家』の執筆にあたり書いたメモだ。1878年のことである。
『堀川波鼓』は、1706(宝永三)年6月に京都堀川で実際に起こった事件を、近松門左衛門が戯曲として書き上げ、翌年2月に竹本座で上演した世話物浄瑠璃である。近松三大姦通物の一つとして知られている。
鳥取藩士小倉彦九郎の妻お種は、参勤交代で夫が不在のなか「やむにやまれぬ事情」で一夜の過ちを犯してしまう。「武家の妻の密通は女も男も死罪」という藩の掟や世間の噂に追い詰められ、自死を遂げる。この過ちに恋愛感情はない。つまり、本気ではなかったというわけだ。そこには、あくまで貞淑な妻としてお種を描こうという、近松なりの気遣いが込められているようにも感じる。しかし、お種の心が動かない結果迎えた “死”であれば、あまりに憐れだと私は思うのだ。自分が取った行動が、この先どんな悲劇を招くか分かっていても、そうせざるを得ない己の熱情にゆり動かされたところに、この女の魂の葛藤と生きる意味があるのではないか。枠をはみ出してはじめて、見つけることのできた自己があるのではないか。
私は、「女の良心」に基づいて、この家庭劇にお種の姿を改めて置いてみた。そこには、原作には無かった切羽詰まった恋情と、産まれることの無かった命への想いも込めたつもりである。
冒頭のイプセンの言葉は、何も知らなければいまの日本のことかと見紛う。そして、江戸時代に起きたこの事件とも、驚くほど通じている。女性を取り巻く状況は、私の周辺では過去数百年まるで変わっていないということだ。
秩序を守るという表向きで、女性に課せられたルールが、女性自身のみならず、異なる性別の人間、そして社会や家族にとって、本当にまっとうなのか…執筆中に感じたこの問いは、私の頭をぐるぐると駆け回り、登場人物たちの動機、人間像へと繋がっていった。
彼らが物語のなかで、何に気づき、どう生きていこうとするのか、ぜひ見届けてほしい。
こうして公演を迎えようとする準備のなかで、いまも戦争の足音が聞こえてくる。いちばんいて欲しいときに、男たちはいない。勇ましい言葉はいらない。私は、ニュースの裏側に隠れた、女たちの声に耳を澄ませていたい。
2022年3月7日
西 史夏