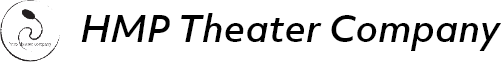現代日本演劇のルーツシリーズ講座編①「古典音楽について学んでみよう!」 レクチャーまとめ
3月12日~13日に上演する『堀川、波のつづみ』の前に、古典の音楽に着目し、古典芸能の魅力や楽しみ方をお伝えするレクチャーと実演を交えた講座を、2021年10月~12月に計3回開催しました。第1回目にとりあげたのは、語り物とよばれる浄瑠璃の1つである「義太夫節」。近代芸能史の研究者である薗田郁さんによるレクチャーをしていただきました。
講座概要
2021年10月16日(土)15:30~17:00@布施PEベース
・レクチャー:「義太夫節のなりたち―語り芸の真髄に触れてみる」
講師:薗田郁(京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター特別研究員)
・実演:傾城恋飛脚「新口村」の段
出演:豊竹呂秀(義太夫)、鶴澤駒清(三味線)
詳細はこちら
レクチャー:「義太夫節のなりたち―語り芸の真髄に触れてみる」
講師:薗田郁(京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター特別研究員)
「『情』を語る」を考える
今日は義太夫節の基礎と歴史を簡単にしまして、「『情』を語る」ところに触れてみようと思います。
みなさんが文楽と口にしたときに、おそらくは「今日は人形浄瑠璃、文楽を観に行こうか」というふうに言うかと思うのですが、昔は「人形浄瑠璃を聴きに行く」というふうに言われています。聴きに行くんですね、舞台を。何を聴きに行くんだろう、というところが気になるポイントです。いろいろ切り口はあると思うんですが、今日は「『情』を語る」というところから考えてみます。
義太夫節の基礎―太夫と三味線弾き
義太夫節っていうのは2人の演者から成り立っているものですね。1人が太夫、語り手ですね。声を使って、声を自在に操って、音楽的にはメロディーやリズムっていうのを駆使して、物語を語っていく人が語り手。そしてもう1人が三味線弾きですね。三味線弾きは太夫を主に支えるような存在ですが、実際には支えるだけではなくて、三味線自身がどんどん引っ張っていく場合もあります。
ちなみに三味線弾きが使っている三味線、「太棹」と言います。三味線は大きく分けて3つ種類がありまして、太棹、中棹、細棹。ですから義太夫節で使われているのは、一番サイズの大きいものですね。厳密にいえば、三味線のサイズっていうのは長さは一緒なんです。何が違うかと言ったら、音を鳴らす胴の部分の大きさが違う。ギターでいうところのネックの部分ですね、左手を押さえるところですが、そこの部分の太さが違う。そのような区別に大まかにいえばなっています。
義太夫節の三味線は太棹を使う、これはよく言われているのは、劇場で大きな声を出す太夫に負けない太い音を出せるように太棹を使っているということです。この2人が、人形浄瑠璃の音楽的な部分を担っている義太夫節ということです。
義太夫節の歴史
―先人の業から編み出された語りの業
義太夫節は、竹本義太夫という人が作り出しました。義太夫は大体17世紀の半ばに出てくるんですけども、いわゆる義太夫節のように物語を比較的メロディーに乗せて語るっていうのは時間をさかのぼって古いところまでいくと、かなり昔から行われていました。
皆さんがよく知っているのと言えば、琵琶を使って平家物語を語る琵琶法師ですね。義太夫節とかが出て来る前に色んなところで語られていました。その琵琶を使って語っていたのは盲人の僧侶だったんですが、はじめその僧侶が平家物語をいろんな形でやっていくうちに、時代が進むにつれて、平家物語だけでなくて色んな物語が語られるようになりました。
そのうち琵琶で語っていたのが、途中で外から三味線が入ってきまして、琵琶が三味線に変わる。そして琵琶法師が語っていた語り方も新しくなります。そういう語りにさらに結び付いたのが操り、つまり人形芝居ですね。そういう風に時代の流れで三味線が入り、語りが新しくなり人形と結び付くことによって、人形浄瑠璃ができるわけです。
義太夫節は、そんな新しい語り物のひとつとして登場した浄瑠璃の1つですが、義太夫節が浄瑠璃を始めたわけではなくて、義太夫節ができる前に様々な浄瑠璃の語り手っていうのがいました。ですので、竹本義太夫はまずはそういう先輩方について学んで、ミックスさせて義太夫節を作りました。
新しいものを作る人って割とそういうところが多くて、自分からゼロからポンと出すっていうよりかはやっぱり、それまでの時代のものを上手く吸収して上手く混ぜ合わせて作る。じゃあ誰でも混ぜ合わせたら作れるかって言われるとそういうわけではなくて、やっぱりそれをどううまく作り上げて、今までにないものを世に送り出すということができるという点で竹本義太夫はすごい人物だったんだろうなと思います。
こういう話をして私が頭に思い浮かぶのは、今年活躍したメジャーリーグの大谷選手です。どっちもできる二刀流って言われてて、みんな二刀流できるけど、それをあのレベルですごいことをやってしまうからこそ今までとは違うような状況がドンと出てきたと。イメージとしてはちょっとスポーツと芸能はだいぶ違いますけど、そういう感じの出方をしたんじゃないかなと思ってます。
―近松門左衛門とのコラボで始まる人形浄瑠璃ブーム
義太夫の人気が出て、人気が出た義太夫にもっと新しい色んな物語をつけて語らせてみようよと言ってコンビを組んだのが近松門左衛門ですね。近松門左衛門が例えばよく知られている『曽根崎心中』ですとか『国性爺合戦』といった作品を提供することで、義太夫節による人形浄瑠璃っていうのがダントツの人気を得るようになりました。竹本義太夫と近松門左衛門の2人が去った後も、全盛期、黄金期っていうのがでてきまして。当時は芸能興行でライバルの関係にあった、むしろちょっとライバルというよりは上の存在であった歌舞伎が既に興行していたんですが、人形浄瑠璃の人気がどんどん出てきて、次のような言われ方もしたんですね。「操り…」、操りっていうのは人形芝居のことですね、人形浄瑠璃のことですが、「…段々流行して歌舞伎は無きがごとし」と。そういう風な状況になります。
―衰退期に登場した文楽軒。そして今へ……。
豊竹座と竹本座の2つが競い合って人形浄瑠璃の全盛期を迎えていましたが、時代の流れで衰退していきます。歌舞伎が今度は盛り返してですね、人形浄瑠璃は苦しくなるんですが、江戸の末期に、淡路島からやってきたある人物がそこで人形浄瑠璃をもうちょっと頑張って立て直そうと奮闘します。その人物が植村文楽軒。今の文楽に繋がるものを作った人ですね。その人が奮戦して、江戸から明治になっても何とか持ちこたえている。ただやはり明治になったら更に色んなものが入ってきますから立ち行かなくなって、結局松竹に引き渡されます。松竹も頑張ったんですけど、松竹もやっぱり無理ですということになって、最終的には今の状況は、大阪府、大阪市、そしてNHKという3つが補助するという形で成り立っている。ちょっとややこしいですね。おそらくこれもみなさんご存じの、もうだいぶ時間が経ったと思いますが、いわゆる大阪市の補助金問題っていうのがあってなかなか。一応今は文楽協会っていうのが文楽のグループとして活動している、ということです。というのがだいぶ駆け足かもしれませんが、義太夫節が出てきた歴史ということです。
「『情』を語る」ことを考えよう
―語り手の感「情」
じゃあ義太夫節の語りとは何でしょう。人形浄瑠璃は聴きにいくものだという風に言われていましたが、語りの何が大事なんでしょうか。
まず、そういう風に聴きに行くっていう状況っていうのはいつ頃まで言われていたかっていうと、割とごく最近。大きく区切れば、戦前までは義太夫節は聴きに行くという状況がありました。じゃあそういう聴衆の人って何を目指して聴いていたのでしょう。その話として、「『情』を語る」という話をしてみたいと思います。ちょっと義太夫節を聴いて感じたある人の言葉っていうのを引用します。
「もう一人の楽師は長い棹のついた日本のギター、白い革の張られた三味線を手にしている。象牙の撥によって、おそらく古代の竪琴にかなりよく似た音を時折爪弾く」という風にあって、ちょっと飛ばして5行目の真ん中ほどから「彼は問いかけ…」彼っていうのは浄瑠璃の語り手ですね、「彼は問いかけ、喜び、不安になり、苦しみ、望み、怒り、怯え、何やら考え、ぶつぶついい、泣き、嘲り、罵り、 疑い、ほのめかし、猛り狂い、怒号し、愛情を示す。その役目は聴衆を惹き付けることである」と言っていますね。これは何かというと、ポール・クローデルという20世紀前半に活躍したフランスの劇作家が人形浄瑠璃を見て書いた言葉なんです。こうやって見てみると、クローデル流石しっかり見ているなという感じで。「『情』を語る」はひとつはこういうことなのかなと思います。(内藤高『明治の音 西洋人が聞いた近代日本』中公新書、2005年、178頁)
ただちょっと、おや待ってくださいクローデルさん?っていう箇所があるんです。それが同じ文章の3行目ぐらいですね。読みますと「この男には言葉を話す権利はない。唸り声と叫び声を上げる権利しかない。胸の奥から直接湧き上がってくる動物的で文字のない音、われわれの中にある舌やさまざまな弁が息とぶつかって生じる音を立てる資格しかないのである」と。最後に飛びますが「ただ言葉(パロール)のみがこの男には欠けているのだ」と…。やっぱり考えてみて「『情』を語る」って言ったときに、ただただ感情を表現するだけではなく、どう表現するかということまで考えるべきだなというのが、逆にこういう人たちの反応を見ると考えさせられるのです。(同書、178頁)
―文句と節で表現する「情」
じゃあ実際どういう風に語られていたのかということで、近松門左衛門に登場してもらいます。近松の考えが表れている唯一の資料の『難波土産』(穂積以貫『難波土産』1738年)の第1巻「発端」という部分をみましょう。これは本人の言葉というより聞き書きしたものを記したもので、近松の人形浄瑠璃というか浄瑠璃観、あるいは芸術観みたいなのが表れていて、非常に重要視されているものです。
ちょっと読みますと、「浄るりは人形にかゝるを第一とすれば、外の草紙と違ひて文句みな働きを肝要とする活物(いきもの)なり」と。それから「正根なき木偶(にんぎやう)にさま〴の情をもたせて見物の感をとらんとする事なれば、大形にては妙作といふに至りがたし」と。「浄るりはもと音曲なれば、語る処の長短は節にあり。然るを作者より字くばりをきつしりと詰遇れば、かへつて口にかからぬ事有物也」と言っています。
まず2番目のところで「情をもたせて見物の感をとらんとする」と書いてあった、確かにここでも「情」という言葉を言ってるよねと。じゃあやっぱり、これはこれでクローデルの言ってることも正しいわけです。ですが、前のところをみるとどうやらそれだけじゃない。つまり、「文句みな働きを肝要とする活物」というのがある。「文句」っていうのは言葉ですね。言葉の働きが第一で、そこに情を持たせるのが大事なんじゃないかということが分かるわけです。ただその言葉と言ったときの語る処は音曲なので「長短は節にあり」。つまりリズムをつけてメロディーをつけてというところが大事。この3つが非常に大事なんじゃないかというところを近松が教えてくれているわけです。
―太夫と三味線弾きの「不即不離」の関係性
義太夫節の語りって大きく分けて3つあるんです。「詞(ことば)」は台詞の部分ですね。いわゆるお芝居を普通にするように台詞をする。「地(じ)」は簡単に言えば音楽的な部分。「色(いろ)」はその間ぐらい、メロディーがあるようなリズムがあるような、でももうちょっと言葉に近いような部分。「地」っていうのは更に「地」の作り方によって6つに分けられます。では語り手さんはこの語りの変化の中で何を気にしているのでしょうか。
義太夫節をずっと研究されてた方の言葉があるんですが、少し読みますと「トップクラスの太夫さんの稽古を傍聴していて、どこがいちばん問題なっているかというと、ことばをどう詰めて語るかということ、すなわち音価の付け方によって意味内容を通じて…」(国立劇場事業部編『文楽』国立劇場事業部、1975年、51頁)あ、すいません、これ私の誤植かもしれないので「…通じやすくすること」という風に言ってます。もう1つ重要だと言ってることは言葉のアクセントですがそれは置いときまして…。つまり語りで大事になのはバリエーションの変化だけど、さらにそこから、言葉をどういう風に伝えるか、そこをすごく気にして語っている。単に弾いて感情を表現するんじゃなくて、その前の段階で言葉をどう伝えるかが先にきている、あるいはそっちが中心にある。その後で、そこから情を足すということが大事になってくるというわけです。
今の燕三さんの前の代の、(五代)鶴澤燕三さんって三味線弾きがいるんですが、その人が語った言葉をご紹介しましょう。「太夫さんが語りまして、三味線が今度チョンと入ります。これがウケですね。…」これは専門用語なんですが「…このウケを間違うと太夫さんが非常に困ります」ということです(井野辺潔監修・義太夫研究会編著『文楽談義―語る・弾く・遣う』創元社、1993年、125頁)。「困ります」というのは、言葉をどう詰めて語るかっというのを常に気にしているので、その辺のお互いのやり取りが非常に大事だからです。
ではどういう風に弾いているか、語っているかということを言い表したものに「不即不離」という言葉があります。つかずはなれずの関係をしているということですね。お互い言葉と意味をどう通じやすくさせるかという意味では同じ目的はあるんですけど、バラバラでもいけないし、絶妙なバランスで出来ているというところです。
―言葉を起ち上げる工夫の先に、「情」が見える
竹本織大夫、これは最終的には竹本源大夫(九代)という方で、もうお亡くなりになりましたけど、その方の言葉もご紹介しましょう。「地色は三味線がこうタッ、タッ、と攻めてきますから、太夫と三味線との本当に火花の散らし合いみたいなところがございますね」(同書、59頁)ということで、バトルのようなところがある。
三味線は支えるだけじゃない、引っ張るところもあるんだという話は、こういうところにも表れています。別の言い方だと「三味線の方が力が上だと、(中略)ダラダラやっていると息もできないほどタタっと弾かれるときもありました」(同書、59頁)ということで、つまりこれは一緒にやってしまうとダラダラして意味内容もダラダラ~っとなって伝わらないと。そこは三味線がピシっとすると言葉の意味が起き上がってくる、ということです。
起き上がり方、これには私の意見も入るんですが、言葉の意味内容を通じると言ったときに、ただ単に意味が分かったらいいかというと、そうではないと思います。その言葉を伝えるのにどんなニュアンスを乗っけていけばいいのかを常におそらく考えていて、だからこそ引っ張ったり伸ばしたり縮めたり早く言ったりする。早く言ったら聞こえにくいかもしれないんですけど、それでも少し言葉を拾いながらその早さの中で言葉のニュアンスを伝える、そういう色々変化する中で、その先に情というのが見えてくるんじゃないかと。そういうようなところを私は感じています。