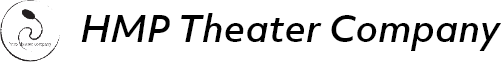『リチャード三世 馬とホモサケル』 インタビュー①
『リチャード三世 馬とホモサケル』がいよいよ来週の11日からはじまります。今回、作を担当したくるみざわしんに、作品やHMPとの共同創作について、インタビューしました。
(笠井友仁へのインタビューはこちらからお読みいただけます)
―『リチャード三世』に取り組もうと思った理由は何でしょうか?
くるみざわ:シェイクスピアシリーズを始めるにあたり、演出の笠井さんから『暴君 シェイクスピアの政治学』(スティーブン・グリーンブラット著、河合祥一郎訳、 2020年9月19日、岩波書店)という本をすすめられました。シェイクスピア研究者のスティーヴン・グリーンブラットが書いた本です。今この時代を共に生きている彼が感じている並々ならぬ危機感を、自分の専門分野を通して語りかけている内容です。この危機感に共鳴し、作品の選定がすすんだように思います。
シェイクスピアが造形した暴君の一人であるマクベスに前作『マクベス 釜と剣』で取り組んだ後、シェイクスピア作品なかで暴君中の暴君であるリチャード三世に取り組むのは自然な流れでした。私の好みや好き嫌いで選んではいません。今この時代に大阪で上演する価値があると判断して作品を選びました。

―前作の『マクベス 釜と剣』でもそうでしたが、原作のタイトルの後に続く、言葉がとてもキーになっていると思うのですが、今回の「馬とホモサケル」の言葉はどのような意図がありますか?
くるみざわ:「馬」は、皆さんご存知の動物の馬です。当時は、戦争になれば戦争の道具として使われていました。「ホモサケル」はイタリアの哲学者ジョルジ・アガンベンの著作を通して知りました。聞きなれない言葉だと思います。新奇な言葉をタイトルに使うことに躊躇したのですが、他に変わる言葉はなく、さんざん試行錯誤した末に「ホモサケル」というカタカナ表記をそのまま使うことにしました。
アガンベンはコロナ禍で国家や医療が生命保護を理由に人間の生活に介入することを厳しく批判しました。親しい人を見舞ったり、その死に立ち会ったり、その死を弔うことを規制する国家に否を突きつけた人です。人間の生に介入する国家の力の源泉は何かを追及し、たどり着いたのが「ホモサケル」という存在です。 国家の力の源泉には、殺してもかまわない、しかし神への生贄にしてはならないという存在―「ホモサケル」がいます。法律の枠の外にいるようで、実は枠の中のさらなる枠の中に放りこまれた存在です。国家は法律を制定し、その法律の力の及ばない例外状態を作り出すことができる。この例外状態に放り込まれた存在が「ホモサケル」で、国家は法律の執行を停止することで、「ホモサケル」を好きなように作り出す。考えたこともない考え方なので、ちょっとわかりにくいかもしれません。「ホモサケル」の具体的な例には、難民・強制収容所などがあります。私もあなたも、国家の意志ひとつで「ホモサケル」になりえます。これが国家の力の源泉です。 今回上演する『リチャード三世 馬とホモサケル』では、「馬」と「ホモサケル」をぶつけることで国家を乗り越えてみようと思います。
―前作でも、今回の『リチャード三世 馬とホモサケル』も、くるみざわさんの作品の軸に、精神医学の考えがあると感じています。 精神医学とはどのようなものなのでしょうか。 また、今作に関しては、精神医学の考えがどのように作品に影響していますか。
くるみざわ:精神医学というのは医学のひとつの分野ですから、「病気」の「治療」を目的にしています。精神の「病気」とは何なのか、どうやったら治るのかを考える学問なのですが、考えを進めてゆくと、精神とは何なのか、治るとはどういうことなのかを考えなくてはならなくなり、さらに考えを進めると、精神医学の考え・姿勢・構えそのものが「病気」の原因なのではないか、精神医学は変わらなくてはならないのではないかというところにたどり着きます。そしてあらためて、「病気」とは何なのか。「治療」とは何のかを考える。この繰り返し―無限の円環のなかで変化を続けるのが精神医学だと私は思っているのですが、そう思っているのは精神医学の世界でも少数です。
精神医学の知識はたいていの場合、脚本の執筆の邪魔になります。精神医学の知識を持ち出し、病名や疾患概念を材料にして登場人物や物語を作ったりすると作品が薄っぺらくなります。慎重に使う必要があります。
今作では、哲学者ジョルジョ・アガンベンの「ホモサケル」という考え方を作品の軸に据えています。その際、ホモサケルを据える土台に精神医学の知識を使いました。「病気」についての精神医学の知識ではなく、どんな人間も持っている根っこの感情―愛と憎しみについての精神医学の知識を使いました。相反し、時にひとつに溶け、また激しくぶつかり合う愛と憎しみの様相を感じ取っていただけたらと思います。

―くるみざわさんとHMPとの共同創作は、2009年の『ユートピア』からはじまり、2015年からスタートした現代日本演劇のルーツシリーズでは鶴屋南北の作品や忠臣蔵三部作をやってきました。 HMPとの共同創作に関して、面白いところ、そして今回、期待するところを教えてください。
くるみざわ:私は社会人になってから本格的に演劇を始めました。戯曲を学び始めたのは37歳を過ぎてからです。高校・大学で演劇部に所属していません。演劇の授業を受けたこともありません。「光の領地」という劇団を主宰していますが、劇団員は私一人です。劇団にいても演劇の話しをする仲間がいません。HMPとの共同創作に取り組むことで、演劇を学んでいます。鶴屋南北、忠臣蔵、シェイクスピアに関心はありましたが、HMPとの共同創作に取り組まなかったら、あれほど深く読みこんで、考えることはなかったと思います。
忘れられないのは「同時代の海外戯曲シリーズ」ですね。私はドラマトゥルクとして関わりましたが、ドイツの作家のデアローアなど、一筋縄では読みこめず、脚本に手を付けることもできない作品を読みこんで、上演のための手直しをし、稽古にも立ち会った経験はその後の創作の糧になりました。
HMPとの共同創作は自由ですね。私を信頼して好きに書かせてくれます。その代わりというわけではありませんが、稽古場で脚本が変わることもあります。私が見落としていたり、思い至らなかったところが付け加わり、さらに面白くなってゆく。
今回は、シェイクスピアのリチャード三世と徹底的に格闘して改作に取り組んだ結果、長い作品になりました。上演時間3時間半です。こんなに長い作品はそうそう上演できませんが、今回、上演が実現します。自信と信頼と実力がなければできないことです。10年以上にわたる共同製作の成果だと思います。
―最後にお客様に向けてメッセージをお願いします。
くるみざわ:観に来て欲しいです。
シェイクスピアはあの時代に、スティーヴン・グリーンブラットもジョルジョ・アガンベンもこの時代にどうしてもこれを伝えなくては思い、演劇を上演したり、本を出版したりして、世に問いを発しています。私達もそうです。私は答えよりも問いに価値がある、たくさんの答えを知っているよりも、たくさんの問いを持つことのほうが大切と考えています。皆さんに私たちの発する問いを見届け、楽しんでほしい。劇場でぜひお会いしたいです。
―ありがとうございました。
公演詳細・チケットはこちら