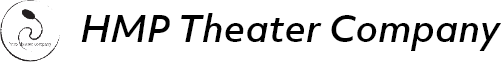シェイクスピアシリーズを振り返る 演出:笠井友仁
「芝居が目指すのは、昔も今も、いわば自然に向かって鏡をかかげ、美徳にも不徳にもそれぞれのありのままの姿を示し、時代の実体をくっきりと映し出すことだ。(シェイクスピア『ハムレット』第三幕二場より 松岡和子訳、筑摩書房、1996年)
クローディアスの悪行を暴くため、自ら書いた台本を上演する直前、役者たちにむけてハムレットはこう語る。シェイクスピアが書き記した演劇の使命は、昔も今も、変わらない、わたしはそう信じている。では、エイチエムピー・シアターカンパニーの「シェイクスピアシリーズ」は、いったい何を映し出そうとしているのか。
この企画がスタートしたのは、2020年10月頃だ。新型コロナウィルス感染拡大の影響で劇場や演劇関係者が大きな打撃を受けており、そのダメージは深刻なものだから、今後、再び多くの方に劇場に足を運んで頂くため、「演劇」の魅力がより多くつまっており、誰もが一度は耳にしたことがある演目を題材に創作しようと考えた。そんなとき、書店を訪れた際、『暴君-シェイクスピアの政治学』(スティーブン・グリーンブラット著、河合祥一郎訳、2020年9月19日、岩波書店)を目にした。ちょうど、自宅時間が増えて、政治とは何か、権力者とは何か、考える機会が増えたので興味深く読んだ。その後、この本の影響を受けて、まずは「暴君」という切り口でシェイクスピア作品をテーマにしようと、くるみざわさんと話した。
(笠井友仁『リチャード三世 馬とホモサケル』インタビュー②、2023年3月3日、https://hmp-theater.com/blog/note/476/)
シェイクスピアシリーズの第二作『リチャード三世 馬とホモサケル』の上演前のインタビューでわたしはこのように答えている。確かに、不安な日々が続いたコロナ禍のなかで『暴君-シェイクスピアの政治学』を読み、シェイクスピア作品に登場する暴君が現代の為政者に重なって見えたことは否めない。ただし、「権力」をテーマにした作品創作は以前から行われていたように思う。例えば、シェイクスピアシリーズの直前まで取り組んでいた、くるみざわしん作『忠臣蔵・三部作(2018年~2020年)』は『仮名手本忠臣蔵』を原作とした将軍を中心とした江戸幕府の権力を描いた作品だ。原作に描かれている魅力的な「恋の話」や「金を巡る話」を割愛し、地方で暮らす赤穂藩士が中央の権力争いに巻き込まれる物語となっている。よって「権力」に注目した作品創作は近年のエイチエムピー・シアターカンパニーの手つきそのものであると言える。では、シェイクスピアシリーズの独自性はどこにあるのか。

シェイクスピアシリーズは2021年11月に上演した『マクベス 釜と剣』から始まった。リーアン・アイスラーの著書『聖杯と剣 われらの歴史、われらの未来』から着想を得て、「釜と剣」が原題に加わった。「釜」とはシェイクスピアの『マクベス』に登場する三人の魔女の持ち物である。魔女たちが食事や薬をつくるさいに使用し、囲んで自由におしゃべりする「釜」とマクベスやダンカン王が常に腰に携え、他者を屈服させるために用いる「剣」を対比させている。さらに、マクベス夫人など、シェイクスピアの『マクベス』に登場する女性に個別の名前が無く、「男性中心の社会」が描かれていることから、『マクベス 釜と剣』において「剣」は男性社会の権力の象徴として、そして「釜」は反権力の象徴として表現された。加えてもうひとつ重要な対立軸がある。それは「城」と「森」である。城は権力が集まる「場」であり、森から資源を搾取することで「城」を中心とした経済が成り立っている。『マクベス 釜と剣』においてマクベス、ダンカン王らは「城」を構えて国が富むことを目指し、三人の魔女は「森」で静かに暮らすことを望んでいる。最後にもうひとつ紹介したい。マクベス夫人がもとは「森」で暮らしていたと語られることである。「森」から「城」に連れて来られたマクベス夫人は男性社会のなかで生きること強いられた人物なのである。そしてマクベスもまた、幼い頃に「森」で暮らしていたことが物語の終盤になって明らかになってくる。マクベスとマクベス夫人は自らのルーツを忘れ、搾取を繰り返していたのだ。
二作目の『リチャード三世 馬とホモサケル』はジョルジュ・アガンベンの著書『ホモ・サケル 主権権力と剥き出しの生』からそのタイトルがつけられた。上村忠男の『アガンベン 《ホモ・サケル》の思想』(講談社、2020年)によると、「ホモ・サケル(homo sacer)」とは、「ローマの古法に登場する、罪に問われることなく殺害でき、しかも犠牲として神々に供することのできない存在」である。くるみざわは「ホモ・サケル」を独自に解釈し、リチャード三世を「死んだまま生きて戦を続ける男」として描いた。戦の神から強大な力を得るため、戦闘前に「自らの葬儀」をあげたリチャード三世は、戦に勝利した後、一滴の血も流さずに勝利の美酒に酔いしれる兄王エドワードや兄ジョージを見て落胆する。そこに戦で亡くなった父の亡霊が「戦はまだ終わっていない」と囁く。その声に導かれたリチャード三世は兄王たちを殺害し、策謀を張り巡らせて「王」となる。シェイクスピア『リチャード三世』は王になったリチャード三世が殺されるが、『リチャード三世 馬とホモサケル』はリチャード三世に支配されて苦しんでいたはずのロンドン市民が知恵を絞り、リチャード三世を殺さずに王位を剥奪し、密かに生かすことを選ぶ。彼らは人を憎むことを嫌ったのだ。リチャード三世は権力を手放すことを恐れるが、権力と無縁だった幼き頃、馬に乗って駆けたことを思い出し、権力の象徴である剣を捨て、馬と暮らしたいと願うようになる。

これまでシェイクスピアシリーズは「権力」をテーマにして「男性中心の社会」に注目しながら、権力が生まれる背景や構造、権力の在り方を表現してきた。では、次回公演『ハムレット 例外と禁忌』はいかなる取り組みか。ハムレットは言葉と行動が一致せず、性格が捉えづらい。父を殺した叔父のクローディアスに復讐する機会を逃し、おもいをよせるオフィーリアを大切にしているのか否かわからない。ハムレットの本心がわからない。そのようなハムレットがオフィーリアの父親のポローニアスを殺害してしまったのだから、オフィーリアも正気を保てるわけがない。オフィーリアが身を投げた後にハムレットは大いに悲しむが、自らにその原因がある。ただしハムレットの置かれている状況も考えねばなるまい。他国がいつ攻めてくるかわからないなか、内側にも危機が迫っているのだ。クローディアスは父のハムレット王を殺し、母親である王妃のガートルードもそれに加担していたかも知れない。ハムレットが正気を保てるわけがない。ハムレットの友人のホレイシオは実によき相談相手だが、だいじな友人を血生臭い復讐劇に巻き込むわけにはいかない。ハムレットが頼るのは亡霊となった父ハムレット王である。権力をふるう「王」。そしてその「王の器」として育てられたハムレットにとって、ハムレット王は手本であり、目指すべき姿である。では、そのハムレットがクローディアスに復讐する機会を逃すのはなぜか。神に祈っているクローディアスを殺すことで彼を天国にやりたくないというハムレット自身が語る理由もわかるが、果たしてそれで権力者が務まるのだろうか、と思ってしまう。ハムレットは理想的な復讐を遂げたいのである。ハムレットの性格の捉えづらさは、このように理想と現実のはざまで揺れ動くためだと考えられる。このように考えてみると、マクベスやリチャード三世に比べて、ハムレットはわたしたちにとって身近な存在のように思えてくる。わたしたちも理想と現実のはざまをウロウロと歩き回り「するか、しないか」といつも考えている。もちろんわたしたちは王家に生まれたわけでない。しかし家族や学校、社会のなかで何らかの社会的な役割を担っている。そして、ときにはその役割がわたしたちのからだにまとわりついて、わたしたちを苦しめる。ハムレットもそれに気づいている。父の姿を追いながら、父とは異なる「自分だけの姿」を探しているのである。
「暴君」を出発点にしながら「権力」を描いてきた〈シェイクスピア・シリーズ〉は『ハムレット 例外と禁忌』をもって一旦、その幕を下ろす。シェイクスピアの『マクベス』、『リチャード三世』、そして『ハムレット』と続くこの試みをたくさんの方にご覧頂きたい。
演出 笠井友仁
公演詳細・チケット:https://hmp-theater.com/work/hamlet/